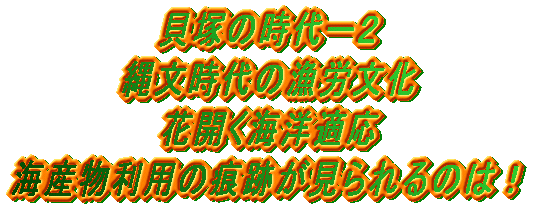
海産物利用の痕跡が列島各地で広く見られるようになるのは、縄文時代早期末から前期(約7000〜6000年前)のことである。それまで急上昇を続けてきた海面は、この時期に現在の海水準より2〜3mほどの高位に達してようやく安定した。
縄文海進がピークを迎えたこの時期、関東地方で海水の及んだ範囲は現在の東京湾をはるかに越えて、江戸川の低地沿いに現在の栃木県南部まで、荒川低地沿いに現在の川越付近にまで達した。今は消滅してしまったこの幻の海は「奥東京湾」と呼ばれている。
海面上昇期の東京湾は、岸から急に深くなるリアス式の海岸に囲まれていたが、海面の安定期を迎えると、河川によって運ばれた土砂などの堆積によって湾内は次第に遠浅となり、沿岸には浅瀬や干潟が徐々に広がりはじめた。こうした湾の浅海化は湾内の生態系に大きな変化をもたらした。
干潟は、家族連れで賑わう潮干狩りの風景に象徴されるように、人間が最も容易かつ安全に接することのできる海であると同時に、内湾の生態系のなかで極めて重要な役割を担っている場所である。
内湾は外洋に比べて陸から流れ込む有機物や栄養分が滞留しやすいため、プランクトンなどの繁殖が活発だが、これらの有機物やプランクトンは干潟において膨大な数の貝類やゴカイなどの棲息を可能にし、それらがさらに多くの魚や鳥などを育む餌となる。
又、干潟に繁茂するアマモなどの群落(藻場)は様々な種類の稚魚たちに隠れ場と餌場を提供している。つまり、干潟は内湾生態系の食物連鎖の結節点として豊かで多様な生物相を生み出すと同時に、天然の養魚場としての役割をも果たしているのである。
縄文海進がピークを迎えた縄文前期は、列島各地でこうした内湾―干潟生態系の発達が急速に進んだ時期であり、これに呼応するかのように貝塚の形成も活発化する。
東京湾岸でもこの時期に貝塚の急激な増加が認められ、特に干潟の形成が早くから進んだ奥東京湾岸や多摩川河口周辺では数多くの貝塚が発見されており、魚介類を食用とする習慣が海岸部に住む人々に広く普及していくさまを示している。ただし、これらの貝塚の多くは小規模であり魚骨の出土量も少ないことから、魚介類は基本的には副食のレベルを超えるものではなかったと推測されている。
全国的に見ると、この時期には極めて活発な漁業活動を展開する地域も見られるようになる。
例えば、縄文前期―中期の大集落である青森県三内丸山遺跡では、前期の地層から多量の魚骨や釣り針・銛先などの漁具が出土し、魚介類が巨大集落での生活を支える重要な食料源となっていたことが明らかとなっている。
出土した魚骨の種類を見ると、サメ類・ブリ・サバ・マダイ・マダラ・ニシン・メバル類・カレイ・ヒラメ・フグなど陸奥湾で獲れる主だった食用魚が殆ど揃っていて、その多彩さは現代の漁獲物と比べても遜色ない。これらの中には、回遊魚、磯魚・底魚類など生息環境や生活様式が異なる様々なタイプの魚が含まれており、大きさも小魚から2〜3mほどにもなる大型魚まで様々である。
特にブリやサバの若魚など、網を使わなければ獲ることが難しい十数cmほどの小魚の骨が大量に出土したことは、網魚法の発達を強く示唆する証拠として注目される。
こうした様相は三内丸山の人々が魚場環境や魚の大きさ・習性などの違いに応じて、釣り、銛、網など多様な技を駆使しながら、陸奥湾で縦横無尽に漁を繰り広げていたことを如実に物語っている。
このように、縄文漁業の基本的な技術要素は縄文前期にはほぼ出揃っていた可能性が高く、以後各地でそれぞれの地域の海洋環境に適応した個性的な漁業の展開が見られるようになる。食用となる植物質源の乏しい北海道では海産物への依存度が特に高く、アシカ類の銛漁やニシン・ホッケなど寒流系の回遊魚の魚を中心とする独特の漁業が発達した。
三陸沿岸では縄文後期以降にマグロ・カジキなどの外洋性の大型魚を対象とした勇壮な銛漁・釣漁の顕著な発達がみられ、九州北西部でも大型のサメ類などを対象とした外洋漁業が盛んであった。九州のサメ漁は対馬海峡を介して朝鮮半島にまで広がりを見せており、漁民たちが文化交流の媒介者ともなっていたことを示している。
一方東京湾、伊勢、三河湾、瀬戸内海、有明海などの内湾域ではクロダイ・ススキ・ウナギ・ハゼ・イワシ類などを対象とした内湾漁業が、又琵琶湖や北上川流域などの湖沼や河川ではフナなどを対象とした内水面漁業が発達した。近現代に至る日本の伝統漁業のなかには、縄文時代に展開したこれらの多様な漁労文化に源流を持つものが多い。縄文文化は、まさに日本人と海との関わりの原点なのである。
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |